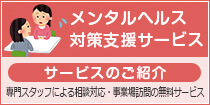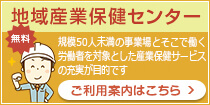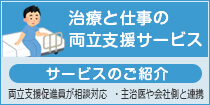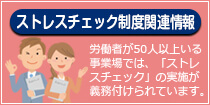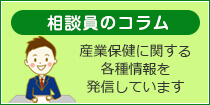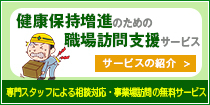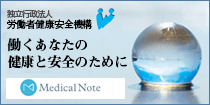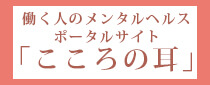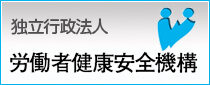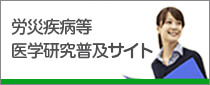産業保健コラム
加藤 ゆみ
所属:オフィス カーム
専門分野:産業カウンセリング・キャリアコンサルティング
性別役割意識の変化
2025年2月3日
最近お父さんが朝子供の手を引いて保育園に通園する姿や、抱っこ紐で赤ちゃんを抱いている姿をよく目にします。私が子育てをしていた数十年前は、保育園の送り迎えや抱っこ紐で子供を抱くのは、お母さん達の役割でした。もしその役割をお父さんにお願いしていたら、少し抵抗感があったかもしれません。
1997年以降共働き世帯数が男性雇用者と無業の妻からなる世帯数を上回り、その差は年々開いています。それに伴い、若い世代の性別役割意識は確実に変化をしているように感じます。世代間のギャップもあり、50代男性上司から、子供のお風呂の時間を優先して、仕事を後回しにして帰る部下への不満をお聞きすることがあります。上司が子育てをしていた当時、母親の多くは専業主婦や家庭優先の働き方をしていたので、そこまで負担は感じなかったのかもしれません。実際夜1人で赤ちゃんをお風呂に入れるのは、なかなか大変な作業です。風呂上がりに、自分は服を着るまもなく赤ちゃんが風邪をひかないよう体をふいて服を着せるのですから、冬場など地獄です。昨今は母親も正職員として仕事をこなしながら子育てをしているので、父親の協力無くしては負荷が高くなりすぎてしまいます。それを思えば、その日中に終えなければいけない業務がなければ、子供のお風呂を優先して仕事を切り上げてもいいのではないでしょうか。
性別役割意識は男性だけではなく女性の中にも根強くあります。奥ゆかしさや控えめを重んじるがゆえに、積極的に前に出ることや強い言葉を発することをためらう女性もまだまだ多いように感じます。「世界経済フォーラム」が公表したジェンダーギャップ指数(2023年)では、日本は146か国中125位です。特に経済や政治の分野では、他の先進国に大きく差をつけられています。
制度がいくら整っても、私たちの中にある意識が変わらなければ職場や社会は変化しません。「男のくせに」とか「女のくせに」など、自分の中にある性別役割意識に、今一度目を向けてみてはいかがでしょうか。
加藤 ゆみ